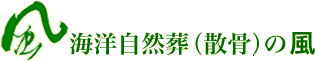癌ステージⅣを5年生きて 86
散骨の風ディレクター KYOKO
子供の頃の夏
私の子供の頃は、映画「オールウェイズ三丁目の夕日」と同じ時代だ。紙芝居を隣町まで追いかけて、妹を迷子にした事がある。レストランを営んでいた私の家は、神田駿河台の中央大学の直ぐ坂下に有り、3階建てのビルで、1階が店、2階の三分の1は宴会場、三分の2が自宅兼スタッフの部屋、3階が貸事務所、1階の一部は喫茶店に貸していた。レストランだったので、普通の家より早い時期にテレビは付いた。金曜日になると店の外に「プロレス中継有ります」と貼り紙を出す。当時は力道山の全盛期だ。試合が始まると店内はいっぱいになり、お客さんが溢れていた。私も力道山が大好きで、大相撲は若乃花のファンだった。
そんな夏いつも嫌な事が起こった。映画のポスターだ。その頃は、町中に映画のポスターが貼られていた。そして夏はいつも怪談のリアルなポスターだった。当時の怪談は本当に怖かった。今の様に心理的ではなく、メイクが本当に震えるほど怖かった。「四谷怪談」は勿論、「番町皿屋敷」、化け猫物も多かった。落語にある「ラクダの馬さん」も本当に嫌で、歩いていてポスターの前に来ると、見ないように横を向いたり、目を瞑ったりして歩いた。夢にも見るし、トイレにも1人で行けなくなった。とにかく超が付く臆病だった。虫も嫌いで、同級生の女の子に蝶々を持って追いかけられた事もある。
そんなに怖がりで臆病なのに、怪談映画を叔母と一緒に観に行く。
何でもないシーンは普通に観ていて、例の「ドロドロドロ」という合図の音楽が鳴ると両手をしっかり顔に当て、目を瞑り、それでも薄目を開けて指の隙間から一瞬見る。そしてまた目を瞑り、耳を塞ぐ。叔母にお化けが消えたら教えてと言う。だから怪談映画も随分観たし、後楽園のスリラーカーにも乗った。でも、お化け屋敷だけは絶対に入らなかった。それでも友達と大人の浴衣やシーツを被りお化けごっこをして遊んだ。
映画少女
私の両親は映画好きだった。その頃は、娯楽が少ないから映画はいつも流行っていた。母のお腹に居る時から映画館に行き、赤ちゃんの時も行っていた。私は映画館では泣かずに大人しくしていたと聞く。そして、物心付くと毎週日曜日は東映の時代劇を、欠かさず観に行った。映画館も多く、東映も大映も歩いて行ける所にあった。このころは封切り2本立て、古いと3本立てだった。子供は50円だったと思う。日曜祭日の映画館は超満員で、座れない事も多く、大人の腰の間を抜けて、前の方に行かせて貰った。私は大川橋蔵と美空ひばりのファンで、美空ひばりは当時のアイドルだった。見終わって映画館を出て行く人達は、みんな幸せそうだった。ささやかだがいい時代だったと思う。私は夜寝る時に大川橋蔵の事を考え、眠りに落ちた。今でも当時の役者はほとんど知っていて、テレビで観ると懐かしい。夫は教育的家庭で育ったから、「笛吹童子」位しか観ていない。それでもお姉さんが石原裕次郎のファンで、映画を付き合わされた事があると言っていた。本人は映画に、それ程興味が無かったのだ。
初めてのミュージカル
中学1年生の時、希望者だけ学校で映画に連れて行ってくれた事がある。「ウエストサイドストリー」だ。場所は学校から近い、スズラン通りの外れ南明座だ。私はミュージカルと聞いて、詰まらないと思っていた。なぜなら江利チエミか誰かが出ていた和製ミュージカルの予告編を見て、とても下らなく思えたからだ。それでも行ったのは、母が「とても良さそうよ」と言ったからである。
映画が始まると、私はファーストシーンから度肝を抜かれた。ニューヨークの街の俯瞰から、いきなり例のJ・チャキリスのダンスシーンに入る。私は、息もつかずに画面に魅入った。すべてのシーンに釘付けだった。そんな体験は初めてだった。見終わっても感動で立ち上がれなかった。館内の皆がそうだった。私はボーっとして外に出た。そして興奮が冷めなかった。家に帰ってもその話ばかり母にしていた。それから私はこの映画を何回観ただろう。観ていないという友達を誘っては観に行った。それからはミュージカルに狂い、サウンドトラックを買っては、歌を覚えた。「サウンドオブミュージック」は、学校行事として、全校で銀座まで観に行った。その頃の中学の校長が映画好きだったのだろうか。東大コースNO.1なのに、教育だけが熱心な学校ではなかった。そしてその時代は、ブロードウェイのいい作品がすぐに映画化された。「ラ・マンチャの男」も「屋根の上のバイオリン弾き」も大好きだ。どの作品も素晴らしい歌がいっぱいあった。最近の物は、歌に物足りなさを感じる。
映画を学ぶ
それまでの私は、時代劇と父に連れられて行くターザンや西部劇位しか観ていなかった。字幕もろくに読めなかったから、本格的洋画に目覚めたのもその時だった。その後は、勤め先で凄い映画マニアたちに遭った。年間150本とか、争うように映画を観ている人たちだ。彼らはチケットを売る仕事もしていたから、半分は仕事で招待券も貰っていた。月末になると余った招待券が私にも回って来て忙しくなった。アングラからやくざ映画まで彼らは何でも観る。私は随分影響を受けて、絶対観るべしとか、監督についてもいろいろ教わった。それまでは、映画スター中心に観ていたから、「山田洋二は好き」と聞かれてあせった。知らなかったのだ。そして先輩の影響で、藤純子の「緋牡丹博徒」シリーズに嵌(はま)り、あんな風に恰好良く行きたいと思ったものだ。映画のシーンを振り返り、本気で、私だったらあの場で、落とし前に指を切れたかしらと悩んだ。
映画の好み
中年を過ぎて、私は意外にも男っぽい映画が好きだと気付いた。「アラビアのロレンス」、「明日に向かって撃て」「マスター&コマンダー」、そして「冒険者たち」はヨットの原点だ。イギリスのBBCで作られた「ホーンブロアー海の勇者」は大好きで18世紀頃の海戦物に夢中になり本も読んだ。海や船の映画には弱いし、男の友情やロマンに泣かされる。アクション映画も戦争映画も一流なら観る。
でも好みとしては、ギリシャ映画「旅芸人の記録」のテオ・アンゲロプロスやロシアの「サクリファイス」タルコフスキー、スペインの「みつばちのささやき」ビクトル・エリセ、フランスの「髪結いの亭主」パトリス・ルコント、オーストラリアの「目撃者 刑事ジョン・ブック」ピーター・ウィアー、イタリアの「愛の嵐」リリアーナ・カヴァーニなど。古過ぎるでしょうね。今は是枝裕和監督が好きだ。
そして、異色な映画、ハンガリーのタル・ベーラ「ニーチェの馬」、モノクロの初めて観る種類の映画だった。ほとんどの画面は茹でた大きなジャガイモを握り拳で潰し、食べると言う日常。食事はそれだけだ。特別な事は起こらず、来る日も来る日も同じ動作の繰り返し、何か起きるのだろうと期待していると何も起こらない。ただ、井戸が干上がり、ジャガイモが無くなるだけだ。それなのに見終わってガーンと来る。カタルシスからショックに陥る。
私は多くを経験出来ない。映画と本はそれを補ってくれる。ポール・ボールズの「シェルタリングスカイ」は、両方が必要だった。本だけでは、想像を超えている部分が多く、映画だけでは分かりづらい。例えば、寿司を見た事のない人に説明しても良く分からない様に、異文化の事は、書いてあっても分からない。特に形ある物や道具、情景、地域的な事は、想像しようがないから、つまらなくても映像が有ると助かる。毎日が新しい経験で、それは尽きる事がない。